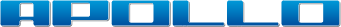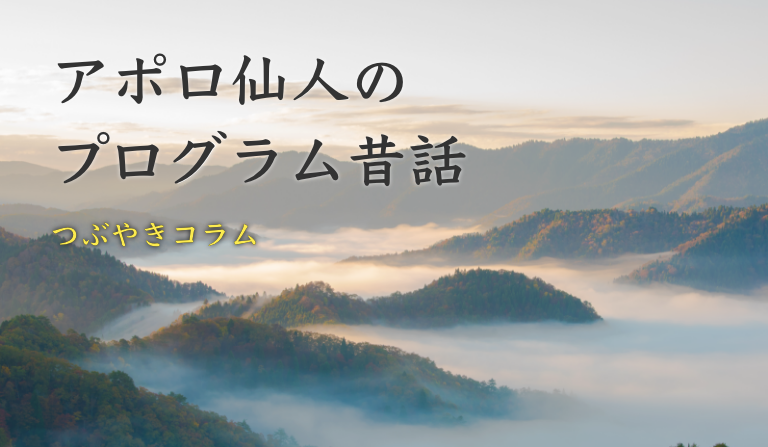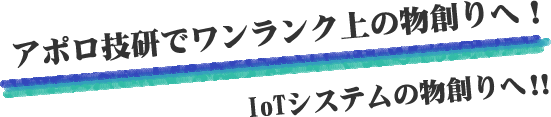第1回:「SI/PI協調解析」って何?なぜ今それが重要なのか?
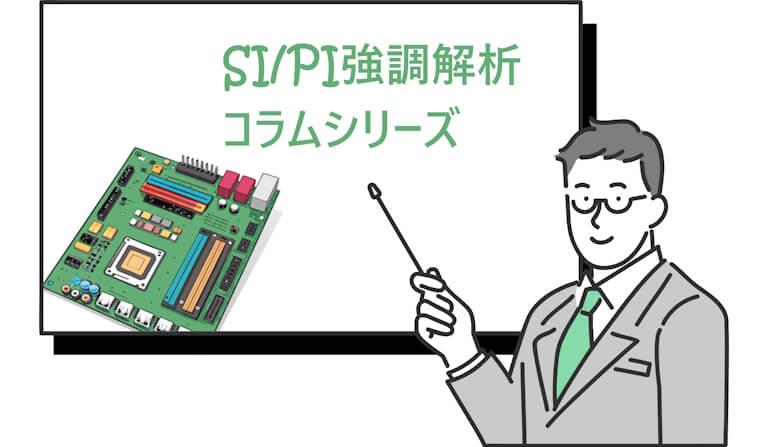
SI/PI協調解析コラムシリーズ
第1回:「SI/PI協調解析」って何?なぜ今それが重要なのか?
~設計のやり直し作業が多くて困っていて更に開発スピードを上げたいお客様へ~
【こんなお悩みありませんか?】
· 最近、基板の試作で原因不明の不具合が増えてきた…
· 高速信号を扱うようになってから、設計が以前より格段に難しくなった…
· SIとかPIとかよく聞くけど、正直何が違うのか、なぜ重要なのかよく分からない…
· 設計の手戻りを減らして、開発期間を短縮したい…
もし、このような課題を感じているなら、今回のコラムが解決のヒントになるかもしれません。
1. はじめに:高速・高密度化する電子回路と新たな課題
私たちの身の回りにあるスマートフォン、パソコン、自動車、産業機器など、あらゆる電子機器は、より高性能・多機能を目指して進化を続けています。この進化を支えているのが、電子回路の「高速化」と「高密度化」です。
しかし、これらの進歩は、設計者にとって新たな課題をもたらしています。かつては問題にならなかったような微細な電気的現象が、製品の性能や信頼性に大きな影響を与えるようになってきたのです。
従来の設計手法では、信号の品質(SI:Signal Integrity)と電源の品質(PI:Power Integrity)をそれぞれ個別に取り扱うことが一般的でした。しかし、回路が複雑になり、動作速度が上がるにつれて、この個別のアプローチでは限界が見えてきました。
2. 「SI/PI協調解析」とは? – 信号と電源は一心同体
そこで注目されているのが「SI/PI協調解析」という考え方です。
· SI(シグナルインテグリティ:信号品質)とは?
簡単に言うと、「信号が設計通りに正しく伝わるかどうか」ということです。
信号が伝送路を伝わる間に、波形がなまったり、ノイズが乗ったり、タイミングがずれたりすると、LSI(大規模集積回路)が正しく信号を認識できず、誤動作の原因となります。インピーダンスの不整合による反射、配線間のクロストーク、タイミングの揺らぎであるジッタ、信号の減衰である損失などが、SIを劣化させる主な要因です。
· PI(パワーインテグリティ:電源品質)とは?
こちらは、「LSIなどの部品に必要な電力が、安定して供給されているかどうか」ということです。
電源電圧が不安定だったり、ノイズが多かったりすると、LSIは正常に動作できません。特に最近は、LSIが低電圧・大電流で動作するようになり、PIの重要性がますます高まっています。
そして「SI/PI協調解析」とは、これらSIとPIを個別に最適化するのではなく、互いに影響し合うものとして、同時に解析・評価し、システム全体として最適化を目指すアプローチです。
3. なぜ今「SI/PI協調解析」が重要なのか?
では、なぜ今、SIとPIを一緒に考える「協調解析」が不可欠なのでしょうか?
· 信号と電源の密接な相互作用:
実は、信号の品質と電源の品質は、互いに深く影響し合っています。
例えば、多数の信号線が同時にスイッチングする(信号の状態が変化する)と、大きな電流が瞬間的に流れ、電源電圧が変動することがあります(SSN:同時スイッチングノイズ)。この電源電圧の変動が、今度は信号のタイミングを狂わせたり(PSIJ:電源由来ジッタ)、信号波形を歪ませたりするのです。逆に、電源ラインのノイズが信号ラインに影響を与えることもあります。
これを家庭の水道に例えてみましょう。
蛇口から出る水の勢い(信号)は、元栓からの水の供給(電源)が安定していることが前提です。もし元栓の供給が不安定になったり、他の場所で大量に水を使ったりすると、蛇口から出る水の勢いが変わってしまいますよね。また、蛇口を勢いよく開け閉めすると、水道管全体に影響が及ぶこともあります。電子回路における信号と電源の関係も、これと似ています。
· 従来手法の限界:
従来の個別解析では、SI解析時には理想的な電源を仮定し、PI解析時には信号の動作を簡略化して考えることが多くありました。しかし、現実の回路では、信号と電源は常に相互に影響し合っています。この相互作用を無視した個別解析では、潜在的な問題を見逃し、試作後に「原因不明の不具合」として現れることがあるのです。特に、低電圧化が進みノイズマージンが減少している現代の設計では、この相互作用の無視は致命的になりかねません。
· 複合的な要因の収束:
· 高速化・高密度化: 信号はよりノイズに弱くなり、部品間の距離が縮まることで干渉が増加しています。
· 低電圧化・大電流化: ノイズマージンが減少し、電源供給ネットワーク(PDN)への負荷が増大しています。
これらの要因が複雑に絡み合い、SIとPIの問題をより深刻化させています。
4. SI/PI協調解析で何が見えるのか?
SI/PI協調解析を行うことで、個別解析では見えなかった問題を発見し、より信頼性の高い設計を実現できます。例えば、
· 電源ノイズが信号品質に与える影響の正確な評価
· 同時スイッチングノイズ(SSN)による電源電圧変動と、それが信号タイミング(ジッタ)に与える影響の把握
· 電源プレーンの共振が信号ラインに及ぼす影響の特定
などが可能になります。
5. アポロ技研ができること
私たちアポロ技研は、長年にわたり様々な電子機器の設計・開発に携わり、このSI/PI協調解析の重要性をいち早く認識し、多くの実績を積み重ねてまいりました。単にシミュレーションツールを操作するだけでなく、お客様の製品仕様や設計思想を深く理解し、課題の本質を見抜いた上で、最適な解析と対策をご提案します。
「SI/PI協調解析についてもっと詳しく知りたい」「自社の設計にどう活かせるか相談したい」など、ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお声がけください。
次回予告:
第2回では、「信号品質(SI)って何が問題になるの?基礎から学ぶ4つの要素」と題し、SIを劣化させる具体的な要因について、初心者の方にも分かりやすく解説します。ご期待ください!